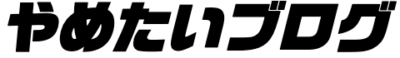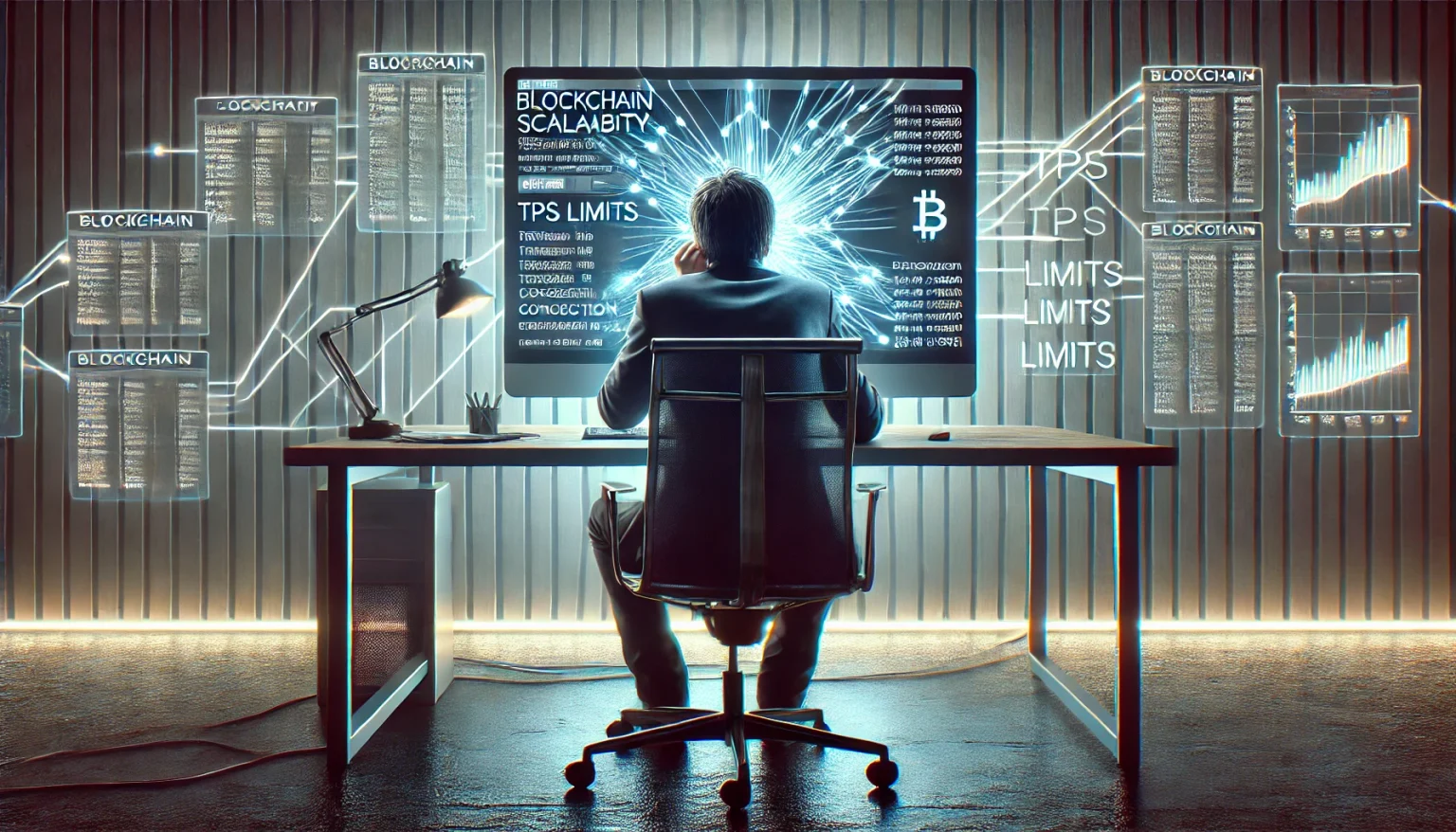皆さんこんにちは。コサキです。
『スケーラビリティ問題』についてざっくり解説しています。
スケーラビリティ問題とは?
暗号資産は、『ブロックチェーン』という仕組みを使って取引データを記録します。
ブロックチェーンを使うことで誰もが取引を確認でき、取引データの改ざんも難しくなるため、透明性と安全性が高まります。
しかし、ブロックチェーンには『スケーラビリティ問題』と呼ばれる大きな問題があります。
ブロックチェーンにおける『スケーラビリティ問題』
ブロックチェーンの元となる「新しいブロックを作る」ためには数分〜数十分の時間がかかることがあり、1つのブロックにはある程度の数の取引しか記録できません。(例えば、ビットコインの場合、1秒間に7回程度の取引しか処理できません。)
そのため、多くの人が暗号資産を使いたいと考えた(取引量=処理件数が増えた)とき、ブロックチェーンは処理しきれなくなります。
現代の決済方法の主流であるクレジットカードは、ネットワーク(例:VISA)上で1秒間に数千件以上の取引を処理できるため、新技術であるはずのブロックチェーン技術の方が速度・効率で劣ることになってしまいます。
例:コンビニ店のレジ
コンビニ店のレジを使って考えてみます。
とあるコンビニには、レジが1台しかありません。レジでは、1回の会計(取引)に数分かかります。
初めは買い物客が少なく、レジ1台でも問題ないかもしれませんが、客が増えれば会計を待つ行列ができて(取引量が増え、ブロックチェーンが処理しきれなくなった状態)しまいます。
この状況では「レジをもっと早くする」か、「レジを増やす必要がある」ということが解決策になると言えます。このような状況を、暗号資産におけるスケーラビリティ問題と呼んでいます。
『スケーラビリティ問題』の解決策
スケーラビリティ問題を解決するために、いくつかの方法が考えられています。
解決策:ブロックのサイズを大きくする
例:レジを大きくして、一度に多くの商品をスキャンできるようにする。
ブロックのサイズが大きくなることで、1つのブロックに記録できる取引数が増え、1秒間に処理できる取引の数(TPS:Transactions Per Second)が増加、取引処理能力が向上します。
ブロックに記録されるのを待つ「未処理の取引」が減り、取引の承認が早くなることで、処理時間が短縮されます。
ビットコインでは、ブロックサイズを拡大するべきかどうかで大きな議論があり、意見が分かれた結果『ビットコインキャッシュ(Bitcoin Cash)』という新しい暗号資産が誕生しました。
ブロックサイズを大きくすることでスケーラビリティ問題に対処しようとした実例です。
解決策:取引をオフチェーンで処理する
例:事前に会計を済ませ、レジでは簡単な確認だけを行う。
ブロックチェーン上での処理を「オンチェーン」と呼ぶのに対し、ブロックチェーンの外側で取引の処理を行う仕組みをオフチェーン(Off-Chain)と呼びます。
オフチェーンで処理する場合、ブロックチェーン上の承認プロセスを経ないため取引がほぼ瞬時に完了し、ブロックチェーン自体の取引量が減る(記録される取引が少なくなる)ことで、ネットワークがスムーズに動作し、手数料を大幅に削減することができます。
オフチェーン処理には、以下のような実例が挙げられます。
ビットコインのオフチェーン技術の一例です。取引を直接ブロックチェーンに記録するのではなく、ユーザー同士が「チャネル」という専用のラインを作ります。このチャネル内での取引は、ブロックチェーンに記録されません。チャネルを閉じる際に、まとめてブロックチェーンに記録します。
イーサリアムのようなスマートコントラクト対応のブロックチェーンで利用される技術です。スマートコントラクトを活用し、複数の取引をオフチェーンで処理した後、その結果だけをオンチェーンに記録します。
解決策:より効率的な仕組みを採用する
例:手動のレジから、自動化されたセルフレジに切り替える。
スケーラビリティ問題を解決するために、ブロックチェーンの基盤となる仕組みやプロトコルを改良し、取引の処理能力を向上させる方法です。
コンビニのレジでの例に置き換えると、「人が手動で商品をスキャンしていたレジから、機械化された自動のセルフレジを利用する」ようなものです。処理速度が大幅に向上し、行列も減らせます。
具体的な解決方法は以下の通りです。
従来のブロックチェーン(例:ビットコイン)は、『PoW(Proof of Work)』という仕組み(計算能力を使ってブロックを生成する方法)で動いており、非効率で電力を大量に消費します。
これを『PoS(Proof of Stake)』という仕組み(計算競争ではなく、トークンを保有する量や期間に基づきブロックを生成する方法)に移行することで、取引処理が効率化され、エネルギー消費も削減されます。
イーサリアムは2022年にPoWからPoSへ移行し、大幅な効率改善を達成した実例があります。
シャーディングは、ブロックチェーンのネットワークをいくつかの『シャード(欠片)』に分け、それぞれが並行して取引を処理する方法です。この方法では、全体の処理能力が向上し、取引が迅速に処理されるようになります。
DAGは、従来の「チェーン型」のブロックチェーンを「グラフ型」に再設計する技術です。これにより、取引が並行して処理されるため、処理速度が飛躍的に向上します。
IOTAやNanoといった暗号資産の IOTA や Nano は、DAGを採用しており、高速で手数料の少ない取引を実現しています。
ロールアップは、複数の取引をまとめて1つに圧縮し、その結果だけをブロックチェーンに記録する技術です。
イーサリアムでは、「オプティミスティックロールアップ」や「ゼロ知識ロールアップ(ZK Rollup)」といった技術が使われています。
これらの代替技術を利用することで、1秒間に処理できる取引数(TPS)が大きく増加(取引速度が大幅に向上)し、取引手数料やエネルギーコストが大きく削減されます。
より多くのユーザーがネットワークを利用しても、混雑が起こりにくくなるため、スケールアップが容易になると考えられています。
「スケーラビリティ問題の解決策」に生じる課題
前章では「スケーラビリティ問題への解決策」も万能というわけではなく、課題があります。
解決策「ブロックのサイズを大きくする」ことで生じる課題
- ストレージ・ノードの負担が増加
ブロックのサイズを大きくすると全体のデータ量も増えるため、ブロックチェーンを保管するストレージや、ノード(ネットワーク参加者)の負担が増える。 - 分散性の低下の可能性
ブロックチェーンのデータ量が大きくなると、個人がノードを運営するのが難しくなり、結果的に一部の大規模なノードだけが運営を担うようになるため、分散型システムのメリットが損なわれる。 - 取引承認の遅延
ブロックのサイズが大きくなると、データを他のノードに配信するのに時間がかかる可能性があり、承認時間がむしろ長くなる可能性がある。
解決策「取引をオフチェーンで処理する 」ことで生じる課題
- 信頼の問題
オフチェーンの取引はブロックチェーンに記録されないため、悪意のある行動が発生する可能性があり、防止するための仕組みが必要。 - 分散性の低下の可能性
オフチェーン処理を行うプロバイダーが集中化する可能性があり、ブロックチェーンの分散性のメリットが損なわれる懸念がある。 - 複雑な仕組み
オフチェーン技術を導入するには、システムやアプリケーションの開発が必要で、導入コストがかかる。
解決策「より効率的な仕組みを採用する」ことで生じる課題
- 技術的な複雑さ
新しい仕組みを導入するには、技術的な開発や適応が必要。 - 互換性の問題
既存のブロックチェーンと新しい技術が互換性を持たない場合がある。 - セキュリティリスク
新しい技術が未成熟な場合、セキュリティ上のリスクが高まる可能性がある。